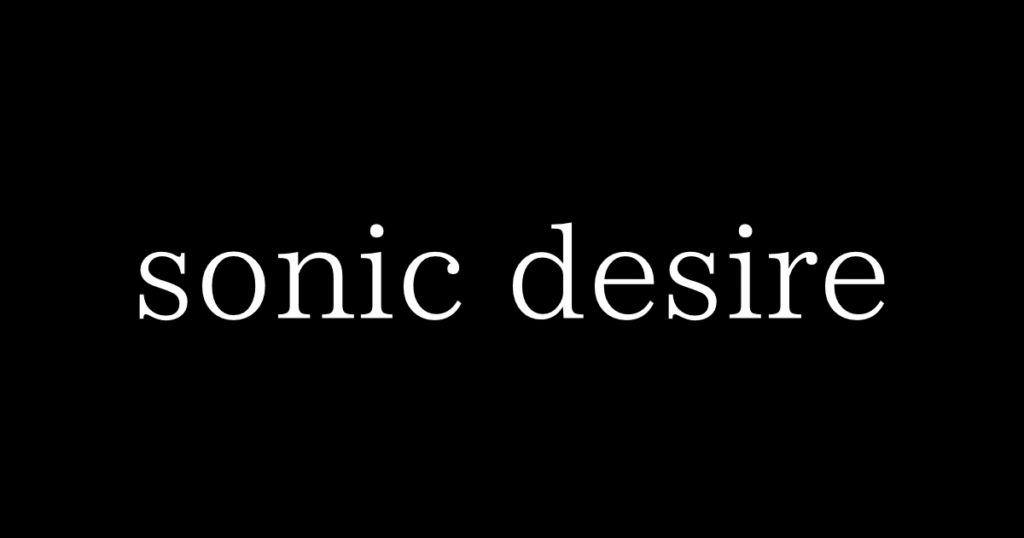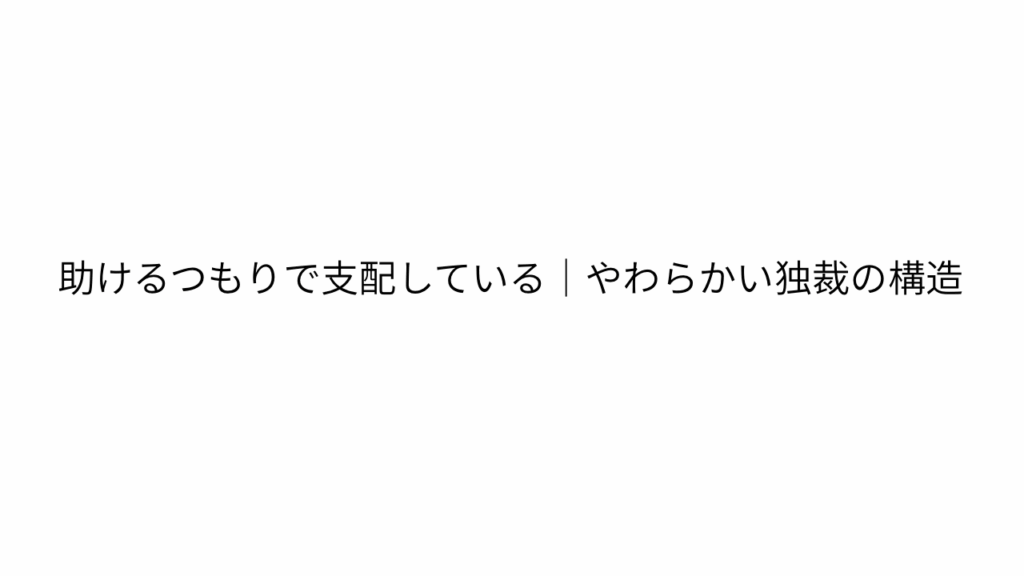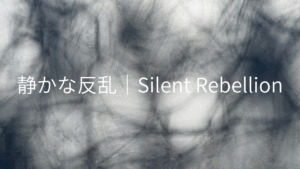最短で稼げの声が街の天井を叩いている。
その下で誰にも要請されていない動作がいくつか続いている。
薄暗いカウンターで水跡ひとつないグラスをもう一度だけ磨く手。
終電後のスタジオで観客ゼロに向けて回るピルエット。
港のフェンスに絡んだビニールを夜風がほどくまで待つ視線。
どれも数値に変換できない。だから価値がないと片づけられる。
そこにこそ研究対象が立っている。
この都市の正義は役に立つかでしか生死を判定しない。
役に立つかは納期と費用対効果で測れる。
測れるものは死ぬまで増やせる。
増やせるものはやがて誰でもできる。
誰でもできることに人はすぐ飽きる。
飽きたあとに残るのが美だ。
美は過不足の計算を拒む。
採算の外にぽつんと立って通り過ぎる者の歩幅を一瞬だけ乱す。
乱された歩幅を誰もメモしない。会議には載らない。
けれどその一歩の乱れが人の一日を微妙に書き換える。
気づかれない書き換えをわたしたちは研究と呼ぶ。
フィールドノート
• ガラス戸の向こう壊れかけのネオンがたまに点く。完全点灯よりもその一瞬の不完全のほうが目を奪う。
• 夜の雨上がり道路の継ぎ目にだけ光が走る。誰の成果でもないが足取りは軽くなる。
• 誰も見ない時間に制服の襟をまっすぐに直す。客単価は上がらない。それでも直す。直すこと自体が人を守る。
効率は世界から偶然を追放する。
偶然が消えると人は驚かなくなる。
驚きが消えると学習は停止する。
利益を最高神に祀る社会はこうして感覚を鈍らせていく。
鈍った感覚はやがて誤差を許さない制度に変わる。
制度は人をまっすぐ運ぶがその途中で景色を奪う。
ここで反転させる。
役に立たない行為をただの趣味や逃避としてではなく社会の劣化を食い止める技術として扱う。
技術には規律が要る。
規律とは誰にも見られなくても続けること。
鑑賞ではなく習慣としての美。
評価の光が届かない場所で手順を研ぐ。
それは無意味ではない。意味が可視化される前に機能するから利益の指標に映らないだけだ。
仮説
• 有益が飽和した環境では不要の精度が人を救う。
• 正しさは人を揃えるが美は人を立たせる。
• 費用対効果の外に置かれた反復は共同体の気圧を安定させる。
新聞は書かない。広告は語らない。
だからここに記す。
端数のように見える作法が都市の体温を保っている。
誰かが無報酬で続ける丁寧さが明日の喧騒を少しだけやわらげる。
この研究は実験室では進まない。
次にあなたがひとりで行う採算外の動作が最前線だ。
最後に線を引く。
計測器を机に伏せろ。
利益表からはみ出した反復を一本だけ自分に残せ。
その一本があなたの生活に静かな地震を起こす。
測ることをやめた場所で美は立ち上がる。
静かな反乱
Night Empire Journal
無益圏研究所
利益にならない美学
無益の美学
感情ブローカー
美学
思想
倫理
価値観
効率主義
文化批評
現代社会
アート思考
無駄の価値
非効率のデザイン